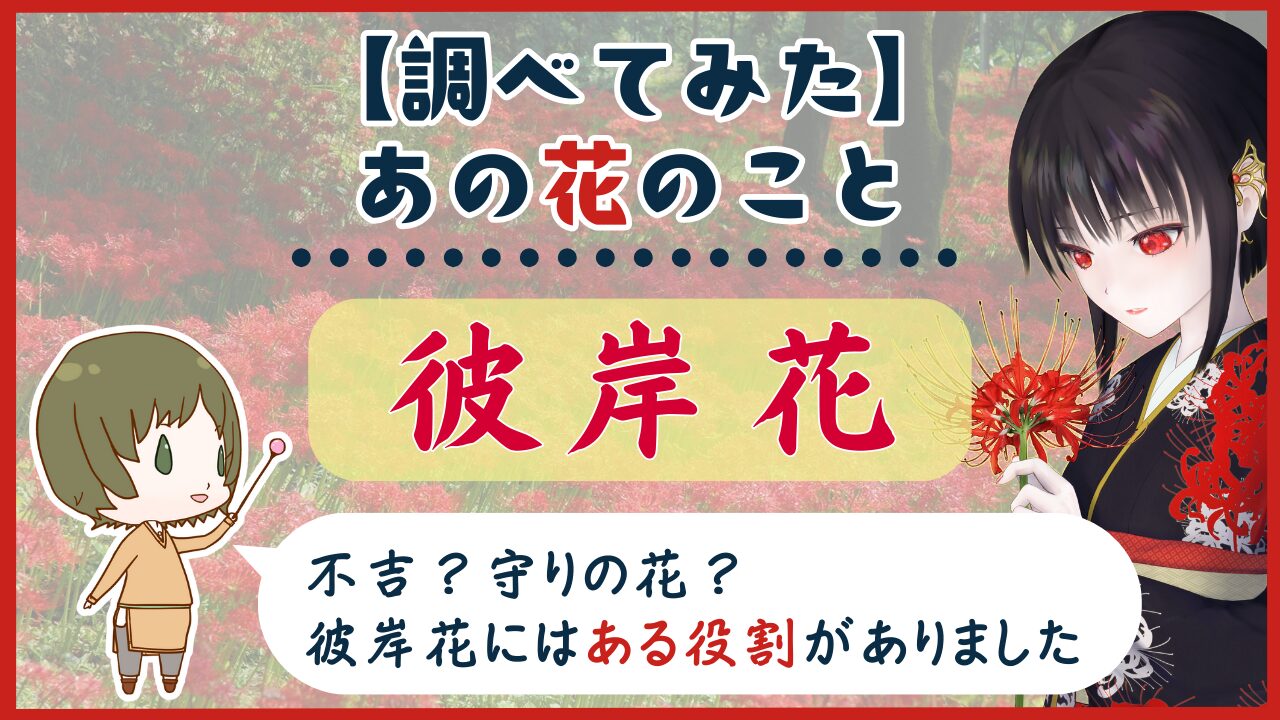田んぼの畦道や川のほとりに、燃えるように真っ赤な花を咲かせる彼岸花。
秋のお彼岸の頃になると一斉に咲き誇り、その鮮烈な姿はどこか妖しげで、見る人を惹きつけます。
一方で「死人花」「幽霊花」など不吉な名前も数多く持ち、独特の存在感を放つ花でもあります。
けれども実は、彼岸花は人々の暮らしを守る大切な役割を果たしてきた花なのです。
秋のお彼岸を彩る花
彼岸花はその名のとおり、秋のお彼岸の時期にちょうど花を咲かせます。
稲刈りを控えた田園風景とともに姿を現し、秋の訪れを告げる風物詩。
日本では「暑さ寒さも彼岸まで」と言われるように、彼岸花は季節の区切りを象徴する花でもあります。
妖しい美しさと数々の別名

燃えるような赤い花弁が放射状に広がり、どこか炎のように見える彼岸花。
その印象的な姿から、人々は多くの呼び名をつけてきました。
- 曼珠沙華(まんじゅしゃげ):仏教の経典に登場する天上の花。
- 死人花・幽霊花:墓地に咲くことから生まれた俗称。
- 狐花・剃刀花:細長く反り返る花びらを狐のしっぽや刃物に例えた呼び名。
美しさと不気味さが同居するようなイメージは、昔から人々の心をざわつかせてきたのでしょう。
実は人を守る花だった
彼岸花にはリコリンという毒があり、食べると強い中毒を引き起こします。
この性質を利用して、昔の人は田畑の畦や墓地に植えました。
- 田畑:モグラやネズミが球根を食べ荒らすのを防ぐ。
- 墓地:遺体や土葬の棺を動物から守る。
つまり「縁起が悪いから墓地に咲く」のではなく、むしろ人々の暮らしと尊厳を守るために植えられていたのです。

文学や信仰に登場する彼岸花
・文学:太宰治や川端康成など、多くの近代文学に登場。「彼岸花=死・別れ・境界」を象徴する存在として描かれることが多く、作品全体に妖しい雰囲気を与えている。詩歌でも「秋の季語」として死や別れの象徴になっている。
・信仰:仏典に登場する「曼珠沙華」としての吉祥的な意味がある。お彼岸の時期とかさなり、「彼岸に咲く花=彼岸花」と呼ばれるように。動物や虫からお墓を守る役割、「死者を守る花」「祖先を守る花」としても信仰的な意味が付与された。
「死・別れ」を連想させるネガティブな印象がある一方で、「吉祥」、「守る」などのポジティブな印象の側面も持ちます。この二つの面があるからこそ、彼岸花は「妖しくも神秘的」な存在として長く語り継がれてきた、といえます。
まとめ
妖しくも美しい姿から「不吉な花」と呼ばれる一方で、実は人々の暮らしを守り続けてきた彼岸花。
その二面性こそが、この花を特別な存在にしているのかもしれません。
秋のお彼岸に咲く赤い花を見かけたら、その背後にある先人の知恵や祈りにも、思いを馳せてみたいですね。
【描いてみた】彼岸花をモチーフにしたイラスト
彼岸花のことを調べているうちに抱いた印象を、自分なりの表現でイラストにしてみました。
ぜひ見ていってください!